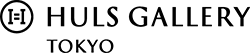現代工芸のキュレーター
現代において、工芸のキュレーターとはどういった存在であろうか。本来、キュレーターとは、日本では学芸員のことを指し、芸術や歴史などを学業として学び、博物館や美術館で働く専門家のことをいうが、今では、独自の目線で情報収集を行い発信する人のことを、そのように呼ぶこともある。私自身は、学芸員の資格を持っておらず、美術館で働いた経験もないが、ギャラリーでは、私自身の美意識で作品を選び、日々お客様に工芸品の成り立ちについて説明をしており、その点でキュレーターとしての役割を担っているとも言える。 工芸は、絵画や彫刻などの美術同様、歴史の深いもので、その知識には際限がない。私も、ギャラリーを運営する以上、日本工芸の作品や産地に関する正しい知識は必要不可欠であり、専門書による学びとともに、作り手の話しも伺いながら、独自で学びを続けている。日本では、陶磁器や漆器、織物など、様々な工芸の分野に関する専門書が出版されており、私のような日本人はそれらの文献を通じて多様に学ぶことができるが、英語や多言語に翻訳されているものは少なく、その点で、私たちがシンガポールで工芸を伝えていくことの難しさと希少さを感じることも多い。 目利きという役割 現代の工芸のキュレーターの仕事として、最も大切な役割の一つは「目利き」だろう。物や情報が溢れる時代になり、それらの価値を見極め、日々の暮らしにどのように取り入れるかは工芸の分野でも益々重要になってきている。目利きを養うには、まずはできるだけ多くの作品に触れること、その中でも名品と呼ばれるものは、いかにして名品となったかをよく理解することが、まずは大切だと思っている。陶芸であれば、古い時代の六古窯の作品に始まり、多くの作り手に影響を与えてきた魯山人や河井寛次郎の作品などは、写真を通じて見るだけでも、その美しさから感じるものは多い。そうした名品からは時代を超えた美意識を学びつつ、現代の作り手の作品には直に触れ、今の社会に求められている美を提案するのが、真の目利きであろうと思う。 調和した展示 また、キュレーターの核たる仕事の一つとして、「展示・陳列」というものがある。展示と聞くと、美術館や博物館の大きな展示会を想像しがちだが、場の大小を問わず、意味を持って作品を美しく展示するということは、キュレーターにとって大きな醍醐味の一つと言っていい。展示というのは、作品一点のみを見て行うものではなく、その周りの作品や環境との調和によって為されるものだ。感じ考えながら一所懸命に行うもので、簡単にさっとできるものでもない。不思議なものだが、私たちのギャラリーのような空間であっても、時と場所によって作品の佇まいは大きく変わるものであり、その変化を読み、独自の世界観を生み出せるようになると、この仕事がますます楽しくなってくる。 キュレーターという言葉は、現代になって用いられているような印象があるが、千利休を始めとする昔の茶人たちが海外の雑器を用いて侘び寂びを表現したり、民藝活動のように、名のない職人の品を民藝と名づけ、新たな美意識を伝えたことは、一種のキュレーターとしての活動であるとも言える。同じように、現代であっても、海外では、日本の工芸品が広く認知されているとは言えず、そこに新たな意味を設け、道を作るところに、私たちの大きな役目がある。その道は、ほんの数日でできあがるようなものではないだろう。日々のひとつひとつの積み重ねが、やがて新しい道を作ることになるのだ。 文:柴田裕介