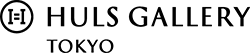学生時代、社会学を学んでいた私は、鷲田清一という日本の臨床哲学者の本を読み漁った。その中に、『「待つ」ということ』という題の本があり、今でも記憶に残っている。
現代人は、待つことに不慣れになってきている。欲しいものはインターネットですぐに手に入るし、携帯電話は待ち合わせの時間を無くしてしまった。暇なときは、スマートフォンで時間をつぶし、周りを見渡すことなく、常に何かに繋がっていないと落ち着かない。そんな時代になってしまった。便利になったと言えば聞こえはいいが、待つことはそれほど無意味なものだろうかと、ふと疑問に思ってしまう。
ギャラリーでお客様に工芸品について説明をする際、工芸品にはたくさんの魅力があるが、時間がかかる点だけは理解してほしいとあらかじめ伝えるようにしている。効率化が求められる世の中には逆行することだが、工芸にとっては本質とも言えるくらい大切なことであるようにも思う。例えば陶磁器の場合、登窯や穴窯を用いる作家は、年に数度しか窯を焚かないことも多く、その時期を逃せば、次に作品に出会えるのは一年後ということもある。また、漆器も、工程の多い輪島塗などは、発注から納品まで半年かかることも珍しくない。移り変わりが激しい世の中では、多くの人が疑問を感じることであろうが、むしろ待つことを前向きに感じてもらうことが、工芸に向き合う心構えなのではないかと思っている。
待つ時間と言えば、お茶や珈琲を淹れる時間も思い浮かぶ。茶葉や珈琲豆を蒸らす時間はほんのわずかだか、ゆっくりと待つ時間は心地がいい。工芸において、用の美は大切だが、使うことと同じく、工芸品が作り出す時間や空間にも、人生の豊かさはあるものなのだ。
思えば、ミケランジェロの代表作である『最後の審判』は5年の歳月をかけて制作されたと言われている。昔の芸術作品には、それ以上に時間を費やしたものも少なくない。そうしたものが今の時代にまで語り継がれている。工芸品も日常的に使っていただくには、効率的に作り、適度な価格で販売する努力は必要だが、時間をかけてこそ美しいものも、少しばかりはあってもいいとは思う。そのどちらもが工芸にとって必要な要素なのだろう。
待つということは、決して時間を失うことではなく、未来を思い浮かべる贅沢な時間なのかもしれない。工芸品を通じて、そんな時間をお届けできたらと思っている。
文:柴田裕介