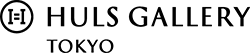「茶の器 2020 夏」開催のお知らせ
HULS GALLERY TOKYOでは、夏におすすめの、涼しげな茶器やうつわが入荷し、7月4日より「茶の器 2020 夏」を開催いたします。 常滑からは、朱泥とは趣の異なる白と銀の明るい色の茶器が届き、愛知県在住の陶芸家・樽田裕史の手による湯呑みと片口は、透かし彫りにした素地に透明釉をかけて焼成する「蛍手(ほたるで)」の技法を用いた、透明感あふれる佇まい。また、有田の李荘窯からは、新たに白磁槌目の宝瓶と湯呑が入荷。シンプルな中にも手づくりの良さを感じることができます。有田からはほかにも、光を通すほど薄い磁器「Egg Shell」シリーズのカップや、見た目も涼しい青白磁の菓子皿も到着。銅器で有名な高岡からは銅製のカップとコースター。冷たい飲み物はもちろん、アイスクリームなどのデザートもお楽しみいただけます。この機会にぜひギャラリーまでお運びください。 ギャラリー企画「茶の器 2020 [...]