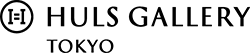ワインと工芸品の共通点
ワインについて、それほど多くの知識があるわけではないが、葡萄の種類や産地の特徴、ヴィンテージの存在など、ワインのことを深く知るにつれて、ワインと日本の工芸品には通じるところがあるのでないかと思うようになった。 ワインは、「天・地・人」によって生まれると言われることがある。この「天・地・人」という言葉は、ブルゴーニュ在住の日本人醸造家である仲田晃司氏が使用した言葉であり、ワインというものは、気候という天の恵があり、土という大地の特徴があり、そこに人の知恵や技術が加わり、生み出されるということだ。「天・地・人」その全てが上手に組み合わさることが最高のワインの条件とされる。海外では「Terroir(テロワール)」という言葉もあり、こちらは地理や気候による土地の特徴を言い表した言葉である。工芸品にも、「天・地・人」や「Terroir」という言葉と同じような性質がある。土地の風土やそこにしかない素材に、人の技が加わる。それら全てが組み合わさることが、美しい工芸品には欠かせない。 ワインは、歴史深く、世界で最も愛される国際的な飲み物の一つだ。5大シャトーのようなワインであれば、美術品と同じような値がつくこともある。ワインがこれだけ世界中の人々を魅了するのは、単純な葡萄の味だけではないだろう。たった一本のワインから、天地の恵みや時の移ろいを感じるところに、その奥深さがある。また、そうした土地や年代の特徴を知ることで、味の違いがわかるようになり、ワインを飲むたびに、どこかを旅するような気持ちにさえなることが、人々を虜にする。 工芸も同じで、私自身、磁器と陶器の違い、木材の違い、産地の文化・歴史など、産地を歩きながら少しずつ蓄えた知識・経験によって、工芸品だけでない物事全般の見方・捉え方が広がってきた。今まで、存在すら意識しなかったグラスは、今では水をも味わう道具となり、暮らしの価値を大きく変えてくれた。その変化は、私の中では、とても大きなことだ。ワインに興味を覚えたのもほぼ同時期であるが、残念ながらまだワインの産地には訪問したことがない。世界の産地を歩いてみたい。そんな夢も膨らんでいる。 日本でもワインの人気は年々高まっており、ワイングラスに取り組む工芸メーカーも増えてきた。意外な接点がありそうなワインと日本工芸。これから先の一つの工芸の道となるのかもしれない。 文:柴田裕介 [...]