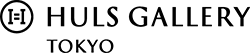木地の山中
「木地挽き」と言えば、石川県の山中温泉が思い浮かぶ。ろくろを用いながら、木を削り出して形を作っていく「木地挽き」は、円形のお椀(椀物)に最適な技法だ。キーンと大きな音を立てて削り出していく姿は、迫力があり一見の価値がある。石川県の漆器は、「木地の山中、塗りの輪島、蒔絵の金沢」と表現されることが多く、山中で生まれた木地は、山中漆器のためだけでなく、輪島や京都など、日本各地の漆器の産地にも供給されている。 山中の木地の最大の特徴は、「縦木取り」と呼ばれる木の取り方にある。木取り(きどり)には、縦木取りと横木取りとがあり、縦木取りは輪切りにしたのちに垂直方向に木を切り抜く方法で、横木取りは木を横にした状態で切り抜くという違いがある。横木取りは最大限に木を活用できることが特徴である反面、強度に欠点がある。一方、縦木取りは、木が育つ方向に逆らわずに木取りするため、変形が少なく、それが薄挽きを可能とする。また、山中の木地挽きは、細かな削り出しを行うことで模様を生み出し、加飾を施すこともできる。「加飾挽き」と呼ばれる山中の技法は日本一と称され、その技の数は数十を超えるとも言われる。その一つに「千筋」と呼ばれる木に細かな筋を入れていく技法があるが、測りを用いず、目視のみで、精密な筋を入れていく技には、驚きを隠せない。 こうして出来上がる木の器だが、用の美としての楽しみは、やはり実際の木目を楽しむことであろう。ギャラリーでは、木製の作品をご購入いただくと、在庫が複数ある場合、在庫品の中から、お好きな木目のものを選んでいただく。これはお客様に木目の多様さを感じていただく大切な時間だ。いくつかの木目の違いを見ていただくことで、自然の豊かさを感じることができるし、その中から選び抜いた品には、特別な愛着を持っていただくことができる。 日本の食文化では、味噌汁や吸い物などの汁物が欠かせず、汁椀の存在はとても大きなものだ。また、日本の汁物は、手にとって食す料理であることから、手に馴染む形状のお椀は欠かせない。陶器の手触りも心地良いが、汁物をいただくときの木椀の温もりは、心まで染み渡り心地よい。木目を眺め、手にお椀を取り、温かな汁をいただく。木地師から生まれた木椀ならではの楽しみ方がそこにはある。 文:柴田裕介 写真:須田卓馬 [...]