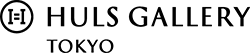人生には、ふとした瞬間に生きている実感を感じることがある。日々の暮らしというのは単調になりがちだが、繰り返しのように見える一日一日も、着実に石は積み上がっていて、あるときその石の形がぼんやりと浮かび上がってくるものなのだ。
2025年3月、シンガポールにて、輪島キリモトの代表を務める桐本泰一さんによる実演販売会が行われた。輪島キリモトは、石川県輪島の漆器ブランドであるが、2024年1月1日に発生した能登半島地震によって大きな被害を受けた。私は震災後に輪島を訪問しており、美しい能登の景色が一変してしまった現状を目の当たりにしている。今回の展示は、そうした輪島の復興に向けての新たな一歩となるべく、特別な想いの込もったイベントとなった。
二日間の実演では、輪島キリモトの得意とする豆鉋(まめかんな)によるスプーン作りが行われた。週末ということもあり、客足は途絶えることなく、多くのお客様にお越しいただいた。輪島キリモトのスプーンは、形の美しさだけではなく、舌触りがとても優れている。私自身も普段から愛用しているが、アイスクリームやヨーグルトを食べる際には欠かせない。今回の実演でも、鉋で削られたあとのスプーンに手で触れたお客様は、その心地良い手触りに大きな驚きを感じてくれていた。
今回の実演から学ぶこと
シンガポールは、自然災害の少ない土地だ。台風や地震がなく、津波や洪水の恐れも少ない。インフラも整っており、暮らしはとても穏やかではあるが、人々はそうした平穏な生活が当たり前のように続き、自然の変化というものがどこか遠い存在のように感じている面がある。また、あらゆる食物が輸入されており、食物は気候によっては不作になるという感覚も乏しい。「A city in a garden」という表現で緑化宣言をしている国だからこそ、自然の豊かさだけでなく、脅威にも目を向けてほしいと思う。
日本では、地震や台風以外にも、自然の変化によってさまざまな困難が発生する。どんなに豊かな暮らしをしていても、思う通りにはいかないことも多い。だからこそ、日々を謙虚に慎ましく過ごし、互いに支え合いながら暮らす文化が育まれてきた。ものづくりも同じであり、多くの工芸品は分業制に基づいて作られており、それぞれの職人の信頼関係によって成り立っている。輪島も例外ではない。被災した輪島では、現在、分業のさまざまな工程で作り手不足が深刻となっており、これまで以上に、地域の中での支え合いが必要となっている。
人生には苦難があったほうが良いというものではない。しかし、望んだままに物事を進めようとする気持ちが強すぎてしまうと、周りとの縁を軽んじてしまいがちだ。縁というものは、片方から一方的に切ってしまうと、修復することはとても難しい。今の時代、都会での暮らしには助け合いは必要ないのかもしれないが、長い人生には必ず誰かの支えが必要なときがある。そんなときにはこれまで築いてきた縁というものの有り難さに気づくはずだ。
私が工芸から学ぶことの一つに、一人では完結することのない「不確かさ」というものがある。漆器であれば、塗師以外にも、道具を作る職人や木地師、蒔絵師など、さまざまな人がいて、漆器産業が成り立っている。綿密に計算して作り上げるものではなく、むしろ互いの信頼関係こそが美しさの秘訣なのではないかと思うことすらある。輪島では、震災によって、一人一人の連なりは今まで以上に大きな意味を持つようになっている。今回の実演は、そうした自然災害の困難さやその後の産地の状況をシンガポールの人々に少しでも伝えることのできる機会になったのではないだろうか。
形のない美しいもの
桐本さんご夫妻とは、シンガポールを案内しながら、さまざまなお話しをした。漆器作りへの情熱はもちろんのこと、工房の職人たちへの想いやお二人の人生観に至るまで、シンガポールに来ていただいたからこそ、長い時間を共有することができた。こうした時間は、私にとって最も貴重なものだ。私たちと作り手は、ただ物を仕入れて売るだけの関係ではなく、互いの暮らしを理解し、夢を語り合い、新たな未来を作り出すパートナーである。少なくとも、私はそうありたいと思い続けている。
イベントは集客、売り上げともに大きな成果をあげることができた。漆器はメンテナンスの難しさから、海外での販売は容易ではないと思っていたが、伝え方次第でこんなにも多くの人々を魅了するのだということに改めて気づかされた。私たちは、工芸品という形あるものにある、形のない美しいものを伝えている。その美しさとは何だろうか。一言で言い表すことはできないが、こうした今回の取り組みには、一つの答えが含まれていることは確かだろう。
何より、桐本さんが私たちの活動やスタッフのがんばりを高く評価してくれたこと、そしてシンガポールという国から多くの刺激を得て、復興への想いを強くしてくれたこと。そうしたことに、私自身も大きな充実感を感じた。桐本さんが展示のあとに、「ここには未来しかない」と仰っていたその言葉が耳から離れない。私は、こんな瞬間のためにこの仕事をしている。そう思った3月のイベントであった。
文:柴田裕介