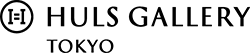新たな土地を訪れるたび、その土地ならではの料理に出逢う。食というのは、国や土地ごとに異なる文化があり、さらには一つ一つの家庭にもそれぞれの味がある。日本には日本料理があり、日本各地の風土やおもてなしの精神とともに、外国人にとって日本への旅行の際の大きな魅力の一つとなっている。
料理は、うつわに盛りつけて食べるものである。ただ栄養のために食すだけなら、調理した鍋からそのまま食べても良いのだが、うつわに盛りつけるという行為は、人々の食事にとって大切なものなのであろう。日本のうつわは、陶磁器や漆器、ガラスに金工など、さまざまな素材からできていて、うつわへの盛りつけにも、独特の美学が備わっている。
日本料理は引き算
日本料理の美学は「引き算」をすることだと言われる。日本料理というのは、えぐみや臭みを引く下拵えを丁寧に行うことで、素材そのものの香りや味を最大限に引き出すことを特徴とする。出汁についても「出汁を引く」という言葉があるように、昆布や鰹節などから旨みを引き出すことが重要とされている。
料理における引き算という考え方は、フランス料理のように、ソースを足すことで味に深みを与えていく料理とは大きく異なる点である。季節ごとに新鮮な食材が豊富に手に入り、素材の味を楽しむことを基本とする日本料理ならではの美学とも言える。
一汁三菜
日本料理においては、「一汁三菜」という言葉があり、米と汁ものを基本として、魚などの主食に副菜を二点添えることを言う。一汁三菜は、もともとは本膳料理の一形式であったが、家庭料理においても、日本人にとっては親しみ深い食卓の風景となっている。
この一汁三菜という形式は、大皿から取り分ける食事とは異なり、日本らしいうつわの文化も育んできた。向付(むこうづけ)という言葉は、懐石料理で出される刺身や酢の物のことを意味するが、飯碗や汁椀の向こう側に置かれるために「向付」と言われる。この言葉は、料理だけでなく、うつわのことも指し、向付にはさまざまな色や形のものがあり、向付には料理人や使い手の個性が表れやすい。
また、日本は四季があることで、衣服だけでなく、うつわにも季節ごとの衣替えがあり、料亭では季節が変わるたびにうつわを変えるのが一般的であり、日本らしいうつわの文化と言えるであろう。夏にはガラスや青磁のうつわ、冬には漆器が合う。酒器も、暖かい季節には薄手の片口が良いが、冬にはやきしめの徳利を楽しみたい。現代の暮らしでは、一年は季節を楽しむ余裕もなく、あっという間に過ぎ去っていくが、食卓にうつわの変化を取り入れることで、単調な暮らしに彩りを与えることができる。
うつわは料理の着物
食とうつわについて語るには、北大路魯山人という人物について触れないわけにはいかないだろう。北大路魯山人は、書家として名声を高めたのち、食や陶芸、漆芸の分野でも活躍し、晩年には会員制食堂である「美食倶楽部」を作った人物である。美食への探究心から、自身で陶芸や漆芸についても極め、彼の食とうつわに対する美意識は、今なお語り継がれている。
魯山人の言葉で「うつわは料理の着物」というものがある。うつわそのものに美が備わっているのではなく、うつわは料理のためにあり、料理を盛ってこそ初めて美しさが宿るということである。西洋料理における白磁のプレートも同じような意味を感じることがあるが、日本人にとってのうつわは、着物と同じように、色や形など多種多様なものがあり、季節や料理との組み合わせともなれば数限りないものとなる。夏にはガラスのうつわに冷奴を、秋には備前焼のうつわに彩り豊かな煮物を盛りつけるのも美しい。日本料理の魅力の一つに、この料理とうつわとの組み合わせの豊富さがある。一つのお気に入りのうつわを使い続けることも楽しいことだが、季節や気分によって、いくつかのうつわを使い分けてみてほしい。そこにまた、新たな食事の楽しみが加わるはずだ。
文:柴田裕介