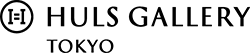漆器の産地に行くと「塗師(ぬし)」という言葉を耳にする。木地を作る人は「木地師」、蒔絵を行う人は「蒔絵師」とも呼ばれ、分業されていた時代の呼び名が色濃く残されている。「木地師」も良い響きだと思うが、「塗師」という言葉は、より重々しく聞こえるのはなぜだろうか。塗師の多くは、畳の上で胡座を組みながら作業をしているのだが、そんな姿が日本の職人らしさを引き立たせているということもある。
日本には陶磁器同様に、様々な漆器の産地がある。「輪島塗」や「山中漆器」は日本人なら誰しも一度は耳にしたことがあると思うが、「越前漆器」「根来塗」「木曽漆器」「津軽漆器」などもある。漆器作りは、漆を乾かすため、適度に湿気があることが必須であるが、木目を活かした塗りの山中漆器と、何層も漆を重ねる輪島塗とは作風は大きく異なるし、高岡のように螺鈿細工を施すことを得意とする産地などもあり、その表現は各地によって様々である。
いずれの漆の産地にも「塗師」はいるが、個人的に「塗師」という言葉で浮かべる産地は石川県の輪島だ。木地に布掛けをし、そこから何層もの漆を重ねていく輪島塗の技法は、現代の効率化社会とはほど遠い工芸品だが、その艶ややかな表情と手触りは、芸術的だ。私が以前にお話をした輪島の塗師である塩士さんは、下地の塗りは他の職人にも任せるが、最後の仕上げの塗りは全てご自身で行うという。塗師としてのこだわりであり、塗師としての生き様なのだと、心を打たれた。
私が工芸を通じて気づいたことの一つは、日本人は時間をかけて丁寧に作ることが得意であり、手間暇をかければかけるほど美しくなる工芸品はとても向いている。輪島の塗師という仕事はその最たるものであろう。輪島に限らず、漆器の産地の塗師の仕事にぜひ目を向けてみてほしい。特に、漆器のお椀は、手に持った際の手触りも十分に考えて作られている。塗師の仕事を手で感じることのできる特別な瞬間なのだ。
文:柴田裕介