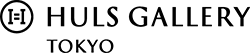工芸品には「一点物(いってんもの)」という表現があり、それは、世の中に一点しか存在しないものという意味を持つ。この「一点物」という言葉は、工芸作家の作品に多く用いられる表現で、蒐集家たちは、自らの好みの一点物に出逢うため、様々な作家の展示会に足を運ぶ。
一点物はこれまでも多くの蒐集家を魅了してきたが、実を言えば、工芸の一点物というのは定義がとても難しい。多くの絵画や彫刻のような美術品は、まさに生涯で一点しか作られない一点物だ。一点物であるがゆえに価値が高まり、人気の美術品は、高額な値段で売買される。一方で、工芸品の場合は、基本は日常で使うものであり、ある数量を作る必要がある。国宝である曜変天目茶碗のようなものでも、今となっては一点物であったかは判断ができず、その時代には大量に焼かれていた可能性も残っている。
例えば、信楽焼の作家が同じ土を使って、薪窯を用いて、茶碗を作るとする。ろくろで作るものであれば、形の自由度は高まり、窯変と呼ばれる窯の変化も加わることで、それぞれの茶碗は二つとない一点物の作品として生まれることになる。ただし、何百個、何千個と作るうちに、見る人によっては似たような作品も生まれうる。そうなると、一点物としての境界線はとても曖昧になる。工芸品においては、明確な一点物は、独創的すぎて日常には馴染みづらい。曖昧さを帯びた一点物こそが、日常の中にはよく似合う。
そんな曖昧な一点物の工芸品だが、それは、綺麗な夕焼けのようなものなのかもしれないとも思う。人生では、似たような夕焼けは何度か見るものだが、そのときの気候や風、光など、様々な要因によって、その日そのときの夕焼けが生まれている。似ているようで似ておらず、全ては一瞬の景色でしかない。工芸品の一点物もそんな存在だと思えば、少しは見え方が変わってくるのではないだろうか。そして、その景色は、その時々の眺める人の気持ちにもよって、美しくもなれば、そうでなくなるときもある。特別な色の夕焼けであっても、下を向いていて気づかないときさえある。工芸品も同じで、曖昧な一点物の価値をどのように感じるかは、その人の感性に委ねられているのだ。
工芸に限らず、服の特注を意味するオートクチュールも根強い人気があり、機械で作られた大量生産品ばかりで現代の日常が埋まるかといえば、そうでもないらしい。私たちの中には、周りと同じでありたいと思う自分と、周りと異なる自分でありたいと思う自分が常に同居している。多くのものをシェアで済ませ、物を持たない現代人が増えているとも言われるが、その一方でこうして希少なものを欲する人もいる。それこそが、これからのアートや工芸の役目になるのだとも思う。
一点物を楽しむには、まず、誰がどこでどのように作ったかを知ることから始まり、その上でその一点の作品に向き合うことに尽きる。他と比べることよりも、目の前の一つ一つに、真っ直ぐに向き合うこと。触れ、使い、時には距離を置いて、遠くから眺めてみる。それは人との向き合い方にも似ていて、とても大切なことでありながら、どこか忘れがちなことでもある。そんなことを、曖昧な一点物の工芸品からは学んでいる気がするのだ。
文:柴田裕介