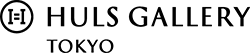物事には、「光」と「影」があり、「陽」と「陰」がある。一般的には、明るいもの、煌びやかなものは美しいとされ、暗いもの、簡素なものは侘しいとされる。谷崎潤一郎は「陰翳礼賛」という本の中で、生活の中の暗がりの在処を見つけ、そこに美を見出すことこそが日本ならではの美意識の一つだと書いた。暗がりの中で見る漆器は美しく、滑らかな光沢とは対局にある和紙の肌理には温もりが満ちていると。21世紀になり、すでに20年が過ぎるが、社会は未だに明るさや清潔さを求めるばかりで、暗がりの在処は忘れられていく一方に思う。その違和感こそが、自分自身が工芸の世界に身を寄せようとする理由なのかもしれない。
工業品と工芸品
「陰翳」というのは、ただの暗闇を指すものではなく、光の当たらない薄暗いカゲを指す言葉だ。光があるからこそカゲがあり、その両者が調和するところにこそ美しさがある。現代の工芸品は、その存在自体が、陰翳の中にあるとも言える。工業製品が輝きある光であるとすれば、工芸品の存在は陰であろう。現代では、工業製品があるからこそ、その昔は当たり前だった工芸品の在処が美しく際立つようになったのだ。高層ビルが立ち並ぶことで、古民家の価値が見直されることや、高音質の音楽が普及するにつれ、アナログレコードの人気が再燃していることにも似ている。昔を懐かしむというだけでなく、そのときには当たり前で気づかなかったものが、主流でなくなり陰のような存在になったとき、突如として、その価値が浮かぶようなことがあるのだろう。
暗がりの中の出会い
暗がりの中では、音や香りも大切な要素になってくる。耳を澄まし、湯を沸かす音を聞いたり、虫の音で夜を彩ることもある。工芸品は、触れたときの音にも個性があり、楽しめるものだ。出来の良い急須や茶筒の蓋を閉じるのは、なんとも言えない心地よさがある。香りも同じく、漆の匂いは独特であるし、天然木の工芸品はやはり趣がある。暗がりに身を置くことで、その感覚が研ぎ澄まされるのは言うまでもない。
社会的活動に関心のある方ならば、一度は名前を聞いたことがあるであろう「キャンドルナイト」。これは、その日一日は、照明を消し、キャンドルの灯りで夜を過ごそうというものだ。スローライフの代名詞のように扱われているものだが、日本の工芸の美に気づくために、海外で、そうした一日を作ってみたいとも思っている。暗がりの中で漆器や竹籠を眺めたり、触れてみる。その感覚は、何か大切な記憶を呼び戻してくれるのではないだろうか。
光が当たるものは無意識にその存在に気づくが、陰翳は、意識して目を向けねばその美に気づかないものだ。現代の工芸品も同じで、伝え続けてこそ、その価値に気づいてもらうことができる。工芸ギャラリーとは、そのためにあるのだろうし、説明せずともわかる光にすぐに流されてはいけまいと、日々自分に言い聞かせている。明るいもの、煌びやかなもののみを見るのではなく、薄暗がりの中で、心静かに何かに向き合っていたい。それこそが、今の時代に必要な侘び寂びに他ならない。
文:柴田裕介