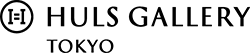あるとき、ふと立ち寄ったお店で購入したうつわ。使い心地が良く、その後、何年も使うことになった。そんな経験はないだろうか。
私が日常で使っているうつわの中にも、そんなうつわがある。思い起こせば、お店の店員が、それぞれのうつわの違いを説明してくれ、そこから、自分の好みにあったものを選んだのだった。あのときの店員さんの説明がなければ、このうつわを買うこともなかったのだと、不思議な縁を感じる。
私たちギャラリーというのは、こうした「縁」を繋ぐことを仕事としている。ギャラリーにとっては、数多くのお客様の一人であっても、お客様にとっては、一つ一つの工芸品との出会いが、特別なものとなることがある。作り手と同じように、使い手にもそれぞれのストーリーがあって、それらを繋ぎ合わせることが、私たちギャラリーの大切な務めなのだ。
日々の仕事
日々の仕事において、基本となるのは、ギャラリーの掃除だ。作品が心地良く並んでいるかを、毎日確認する。うつわの多くは、手に持ち、口につけるものであり、常に清潔さを保たなければならない。仕事に身が入らなくなると、まずはこの掃除が疎かになっていく。掃除は、その場所をきれいにするだけでなく、自らの心を落ち着かせることにも繋がるものであり、常に意識して行う必要がある。
また、ギャラリーには、頻繁に新しい作品が届くのだが、それらの一つ一つに関心を持ち、丁寧に向き合うことも大切だ。私は、自分自身で作品の撮影をするが、その時間を通じて、作品にじっくりと向き合うことができる。どこから見たら美しいか、どのように使ってもらいたいかなど、作品一つ一つの個性を確かめながら、いろいろな思いをめぐらせる、私自身にとって好きな時間でもある。
作り手のバトン
私たちのギャラリーの仕事は、「ストーリーを伝える仕事」と、よく説明される。確かにその通りで、私たちは良い「語り手」でなくてはならず、作り手や物の知識を学ぶだけでなく、姿勢や話し方なども磨き続けなくてはならない。
また、私たちは、作り手の「少しでも良いものを作りたい」という気持ちを、バトンとして受けとっている。一つずつ人の手で作られたものだからこそ、丁寧に包み、袋に入れ、直接手でお客様にお渡ししたい。そして、お店から出るまで、きちんと見送り、挨拶をする。そうした一つ一つのことに、「気持ち」というのは込められていて、ようやく作り手のバトンは心地良くお客様に渡っていく。
作り手と同じ熱量で
私は、工芸の仕事をする上で、いつも心に語りかけていることがある。それは、作り手と同じ熱量で仕事をするということだ。私たちのギャラリーは、東京とシンガポールという、都会の暮らしの中にある。都会では、仕事は仕事と割り切る人も多いだろうし、自分のキャリアアップや趣味の時間こそが人生の目的という人も少なくない。けれど、工芸の作り手はどうだろうか。思うに、良い職人というのは、暮らしと仕事の明確な境界線はなく、暮らしながら働いているような職人が多いのではないか。そういう人たちの手仕事の日常を思い浮かべながら、私たちだけが都会の時間に合わせてはいけないのだと、心に言い聞かせている。
また、職人というのは、何年もの修行を経て、一人前の仕事ができるようになると言われる。天然の素材であるがゆえに、まずは数を作らなければ、その素材を使いこなせるようにならない。そのような作品を扱っているのだから、私たち販売する側も、同じように長い年月をかけて、自分の目利きをじっくりと養っていく必要がある。いくつもの作品を見て、触れて、初めてその良し悪しがわかるようになってくる。
工芸品は、刺激的な日常を生むものではなく、長く時間をかけて触れてこそ、いつしか、その美しさや魅力に気づくものだ。日々の一歩一歩は、ゆっくりかもしれないが、あるとき、必ずやその道の大切さを感じられるようになる。それが、人々が生み出す文化というものであり、伝統というものなのだ。
文:柴田裕介