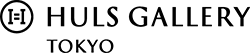現代の工芸品は、全ての工程が手で行われているとは限らないが、その多くが手仕事であることには変わりはない。手で作られたものには、独特の温もりと素朴さがあり、その魅力がすぐに失われることはないだろうが、機械生産の高品質な日用品に慣れ親しんでしまっている私たち現代人にとっては、手仕事のものに触れる際には少しばかりの心構えが必要だとも思っている。
この先の未来では、AIや自動化が進み、いずれは食材だけを用意すれば、美味しい「手料理」を作ってくれるロボットが登場し、家で食事を作ることも激減するかもしれない。工芸品も例外ではなく、人の繊細な手業を機械が完璧に再現する日もそう遠くないだろう。それでも、故郷に帰ったときに食べる手料理は、どんな料理とも比べることができないように、人が手で作るものへの愛情は、もうしばらくは変わらないだろうと思う。
未来に、工芸のような手仕事はどうあるべきなのだろうか。もちろん、使う人にとって、手仕事のもののほうが素朴な手触りがして、親しみが湧くということもあるだろうが、それ以上に、作り手側の気持ちとして、物を手で作ることが楽しいということも大事なことではないかと思う。楽器を弾いたり、食事を作るなど、手を使うということは、人にとって大きな価値の一つであり、決して効率的で生産的だからといって、安易に機械に置き換えてよいものでもないだろう。工芸品に触れていると、作品としての美しさを感じる一方で、作り手が楽しみながら作ったかがわかる瞬間というものがある。一例を挙げると、信楽焼作家の澤克典さんの絵付け作品からはそうした手仕事の楽しさが感じられ、明るい気持ちにさせてくれる。
仮に技術を完璧に再現したものがあったとして、そこにそうした感情は生まれるものだろうか。誰かが手で作ったという事実は、とても大事なことであり、まったく同じものであっても、おそらく心への響き方は大きく異なる。人の手というものは不思議なもので、様々なことを作り上げてきた歴史がある。人の手の可能性をもう少しだけ掘り下げてみたい。そんな気持ちすらある。
使い手として手仕事に向き合うには、不揃いを個性だと感じる「目利き」も必要になる。今の時代、不揃いを個性と感じることは、簡単なことではないだろう。特に西洋文化では、家庭で同じ食器を多く揃えるのが一般的で、見た目が綺麗に揃っていることを美とする。一方で、日本の一般家庭では、飯碗やお箸は、それぞれで異なるほうが一般的であるし、家庭の中でもこれはお父さんのお碗、これはお母さんのお箸とそれぞれが愛用するものを使うのである。同じかどうかを見る目よりも、異なるものの個性を見出す美意識を広めたい。それが、こうした日本工芸ギャラリーの役割の一つでもある。
手仕事の工芸品の魅力をより感じたいと思う方は、自分も手を使って何かを始めてみてほしい。簡単な手料理でもいいし、絵でも楽器でも良いだろうと思う。そして、それを誰かのために行ってみると、手仕事の美しさと難しさが身近に感じられるようになる。手仕事に明るい未来があるかと聞かれれば答えは難しいが、手仕事で未来は変えられるかと聞かれれば、自信を持って、変えられると答えたい。日々、作り手と向き合いながら、そう思うのだ。
文:柴田裕介