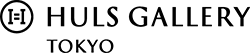「色」は、文化の一つであり、美的な表現の一つでもある。もしも、それぞれの文化が固有の色彩を持たなければ、文化の境界線は曖昧になり、ここまで美術や工芸は各国独自の発展を見せなかったであろう。欧州のように地続きの国々でさえ、それぞれには独自の色の文化がある。自然環境はもちろん、宗教や思想、ファッションなどからも影響を受け、色は様々な発展を遂げてきた。日本も、豊富な自然と四季の存在により、他にはない色の文化を作り上げてきた。燻んだ色にも意味を与えながら、桜のように美しい花が色の名になることもある。金銀は、金閣寺・銀閣寺はもちろんのこと、美術史においては琳派の世界を思わせ、日本の美意識が大きく映し出されている。色を知ることは、その土地の美意識を知ることであり、工芸においても、大切な要素の一つなのだ。
私自身は、以前から色の世界が好きで、いつか色についてきちんと学んでみたいと思い続けてきたが、工芸の世界に足を踏み入れ、織物の草木染めの世界に触れたことで、これまで以上に、日本の色の美しさに深い興味を抱くようになった。工芸の色と言えば、陶磁器の染付や赤絵、漆器の朱や黒、木版摺りの色彩などが思い浮かぶが、日本の草木そのものの色を映し出すという点で、草木染めは色表現の代表的な存在と言っていいだろう。
私が初めて草木染めに触れたのは、小倉織の染織家である築城則子さんの工房に伺ったときのことだ。築城さんは大学在学中に、能装束の魅力に出会い、そこから染織家としての道を歩み始めた。その後、自身の故郷で一度は途絶えてしまっていた小倉織を復元することに成功。そこからは小倉を拠点として、精力的な活動を続けている。文学を愛する築城さんの色世界は、深くそしてどこまでも広い。築城さんの作品は、縦縞のグラデーションを特徴とするものだが、グラデーションを表現するには、一つの色に対し多数の濃淡が必要で、染める作業だけでも多くの時間を要する。築城さんの工房には多数の色糸が保管されているが、それを染めた歳月を思うと、自然の広がりを感じざるをえない。「青」と一言で言っても、「群青」「瑠璃」「紺碧」など、無数の青があり、ひとつひとつに意味がある。名づけた人の感性も素晴らしいが、それを伝え繋げてきた言葉のリレーも美しい。
私は、別の国に訪れると、まずは匂いと色が日本とは異なることに意識が向かう。色が異なるのは、物に備わる色だけでなく、光や湿度による影響も大きいのだとは思うが、そうした環境の違いの中で、どんなものがその国で最も美しいとされているかを想像することが楽しい。異文化の壁を超え、日本の工芸品を伝えていくことは、日本の色が海を渡ることでもあり、色の説明も続けていくべきなのだろうと思う。いつしか、日本の色をテーマにした工芸の展示を行いたいと思っているが、それはきっとそう遠い未来の話ではない。
文:柴田裕介